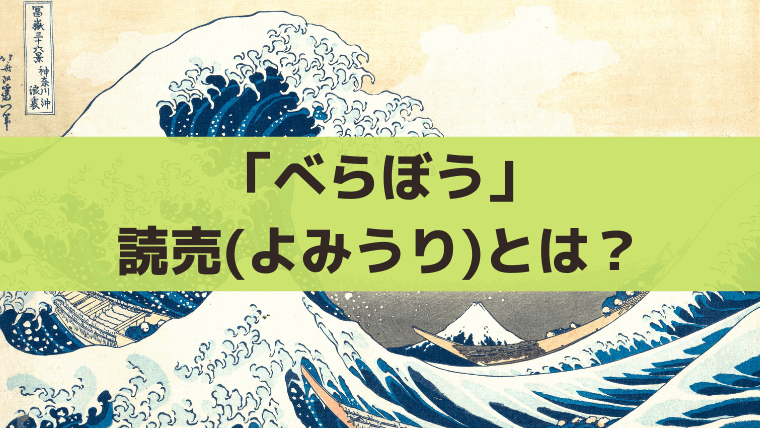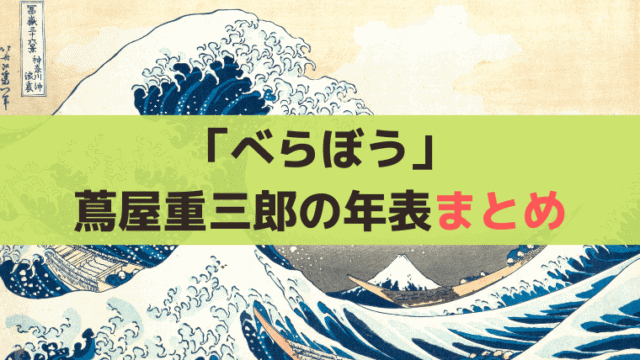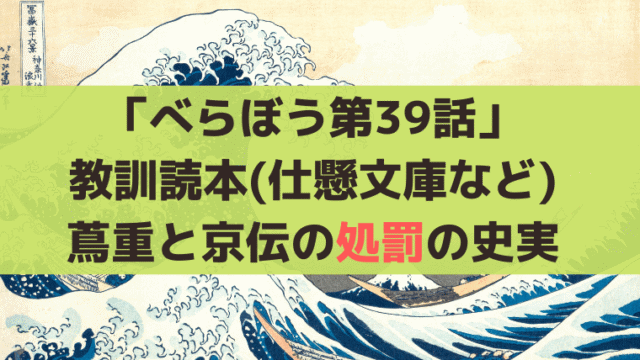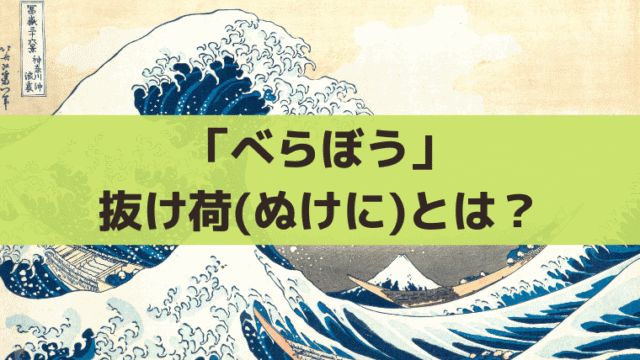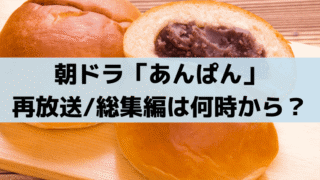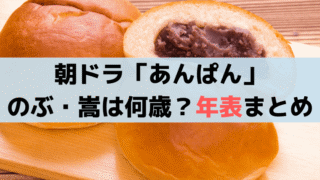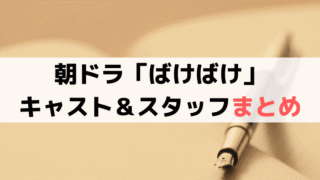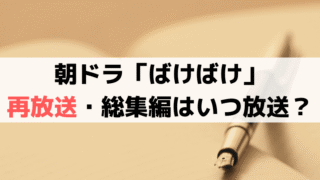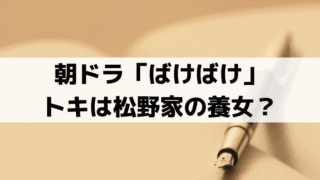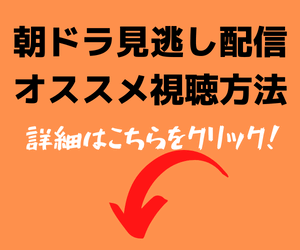2025年1月5日(日)スタートの第64作となるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」
「べらぼう」の主人公・蔦屋重三郎を演じるのは「横浜流星」さんです。そして、森下佳子さんが脚本を担当、あらすじは以下の通りです。
“江戸の出版王”と呼ばれた「蔦屋重三郎」の波乱万丈の生涯を描く。人口100万を超えた江戸、貧しい家庭に生まれた蔦重は養子として育ち、貸本屋から書籍編集・出版業へと進出。
田沼意次の時代に「黄表紙」の大ヒットで文化の中心となり、喜多川歌麿や葛飾北斎など、後の巨匠たちを世に送り出す。笑いと涙、謎が交錯する物語を通じ、蔦重の自由と文化への情熱が時代を超えて描かれるエンターテインメントドラマ。
「べらぼう」第32話では、蔦重(横浜流星)が「読売(よみうり)」を発行する展開が登場します。
江戸時代の「読売」は、現代の新聞の元祖とも言われる“江戸の瓦版(一枚刷りの印刷物)”の一種でした
【べらぼう第32話あらすじ】田沼派の巻き返しと、蔦重が「読売」を出版

「べらぼう」第32話では、田沼意次(渡辺謙)の復帰をめぐる政争がさらに激化。
田沼派の水野忠友(小松和重)や松平康福(相島一之)は謹慎を続ける意次(渡辺謙)の復帰に奔走し、意次は再び登城を許されることになります。
一方、蔦重は「意次の政策は人々のためになっている」と感じますが、長屋の住民からは逆風が。「田沼時代に得をした人」として反発を受け、葛藤する蔦重。
そんな中、意次の家臣・三浦庄司(原田泰造)から頼まれた蔦重は「救い米が配布される日」を「読売」に掲載して発行することになります。
また、蔦重が三浦に頼まれて「読売」を発行したという史実は確認されていません。「べらぼう」のオリジナルエピソードです。
江戸時代の読売(よみうり)とは?庶民に広まった瓦版ニュースの役割と特徴
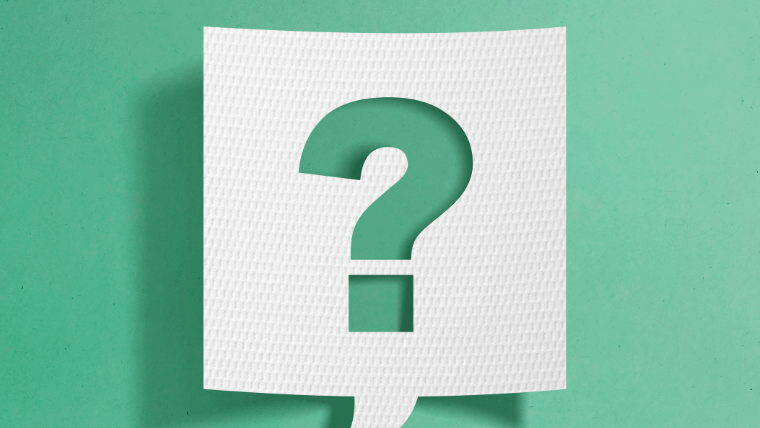
江戸時代の「読売(よみうり)」とは一枚刷りの印刷物に、時事的な出来事や事件、芝居の情報などを記載し、庶民に向けて販売されていました。
情報の伝達手段が限られていた時代において、読売は庶民にとって身近で貴重なニュースメディアでした。
江戸時代の「読売」とは?町で読み聞かせながら売る瓦版ニュース
「読売」の特徴は、売り手が町を歩きながら記事を声に出して読み上げ、そのまま瓦版を販売するスタイルにあります。
声を張って内容を伝えることから「読み売り」が「読売」という呼び名につながりました。
文字が読めない人々にも情報を届ける“音声メディア”的な役割を持っていたのも大きな特徴です。
価格は手ごろ、内容は身近、江戸庶民の「リアルタイム情報源」
読売は一枚ずつ刷られ、価格は数文程度と手ごろ。庶民でも買える安さで、生活に直結するニュースを伝えていました。
扱う内容はさまざまで、たとえば…
- 芝居や見世物の案内
- 火事や犯罪、事件の速報
- 政治的な噂話
- 異国の情報や珍しい話題
など、「庶民が知りたいこと」をわかりやすくまとめたものでした。
読売は現代新聞のルーツ!読売新聞の名前の由来に
「読売」は、市中に情報を広め、庶民の暮らしを支える存在でした。速報性と手軽さを備えた「読売」は、まさに現代の新聞のルーツの一つといえるでしょう。
そして、現在まで発行されている「読売新聞」の語源は、明治初期に創刊された当初の販売方式である、江戸時代の「読みながら売る」という「読売」に由来しています。
まとめ
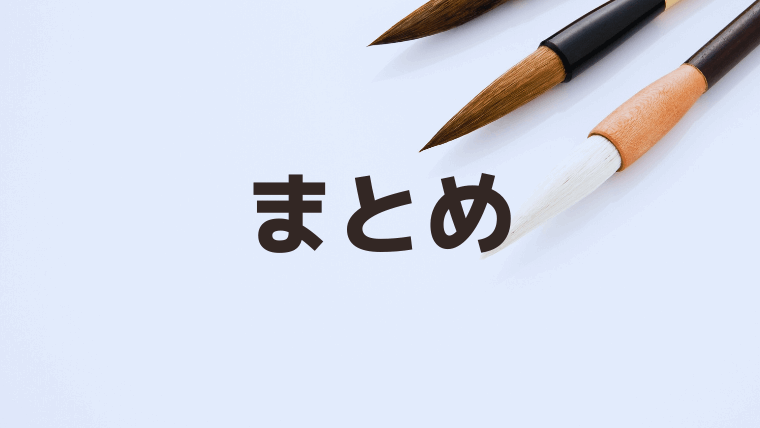
「べらぼう」第32話に蔦重が出版した「読売」は、現代の新聞のルーツともいえる存在です。
情報の伝達手段が限られていた当時において、「読売」は“庶民のリアルなニュースメディア”とも言える存在でした。
他にも「べらぼう」のキャスト・登場人物・スタッフ一覧は、以下をチェックしてください。
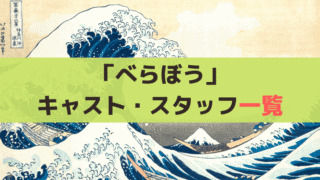
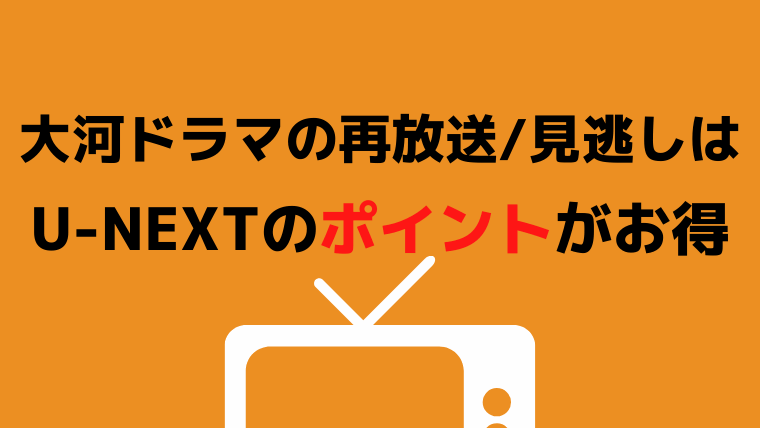
無料の「NHK ONE」は放送後1週間分の、「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の見逃し視聴が可能です。
ただし、過去1週間以上前の大河ドラマを見るためには、有料の「NHKオンデマンド」の契約が必要です。※ドラマの放送があった1週間後から、「NHKオンデマンド」配信されます。
動画配信サービス「U-NEXT」経由で契約すれば「31日間無料トライアル」「初月1,000ポイント」もらえるので、ポイント利用で「NHKオンデマンド」のお試し視聴が可能です。
過去作「光る君へ」「どうする家康」「鎌倉殿の13人」なども見放題です。
\ お試し視聴可能 /
※2025/10/02時点の情報です。最新情報は「U-NEXT」公式サイトで、ご確認ください。
また、「U-NEXT」をオススメしている理由、注意点などは以下で解説しています。